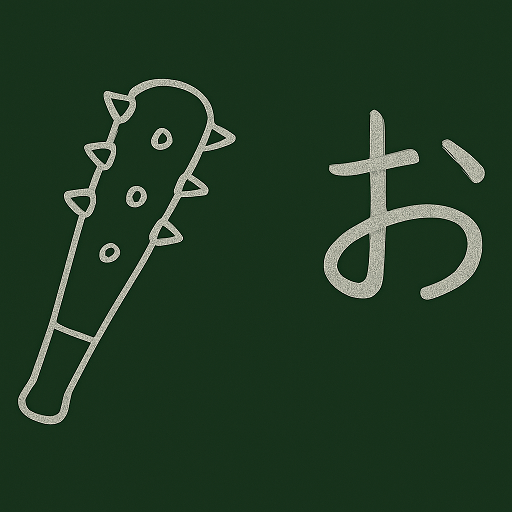
「お」ではじまるビジネス、経済学関連の格言や言い回しです。
岡目八目/傍目八目(おかめはちもく)
当事者よりも、第三者のほうが物事の本質を冷静に判断できるということ。
【解説】ビジネスにおいて、当事者は利害関係や感情にとらわれやすく、誤った判断をしがちです。一方、外部の第三者は冷静な視点を持てる場合が多く、投資や経営の判断の参考になる意見を求めることもできます。
【英語】Lookers-on see most of the game.
起きて半畳寝て一畳(おきてはんじょうねていちじょう)
人が実際に使う空間はわずかであり、過度な贅沢は無意味であるということ。
【解説】どれだけ広い家や立派な住まいを持っていても、人間が生活に本当に必要とする空間はそれほど大きくありません。これは経済学的には「限界効用逓減」や「消費の飽和」に関連します。所得が増えても、生活満足度が比例して増えるとは限らないという事実とも一致します。「起きて三尺寝て六尺」ともいいます。
屋上屋を架す(おくじょうおくをかす)
すでにあるものに、さらに不要なものを重ねる無駄な行為。
【解説】効率性が求められるビジネスや経済政策において、「屋上屋を架す」は過剰な手続きや制度などを意味します。
【出典】
〔顔氏家訓・序致〕「魏晋巳来、著す所の諸子、理重なり事復し、……猶お屋下に屋を架し、牀上(しょうじょう)に牀を施すがごときのみ」
(魏・晋以来、多くの人々が著した書物は、その道理も事実も重複していて、ちょうど、屋根の下に屋根を作り、寝台の上に寝台を設けるのと同じである。)
※原文は「屋下に屋を架す」
教うるは学ぶの半ば(おしうるはまなぶのなかば)
人に教えることは、自分自身の学びにもなるということ。
【解説】経済学の講義や教育の場でも、教える側が最も深く理解するという現象はよく見られます。これは知識の定着や構造化にもつながり、学習効果が高い方法です。→教育経済学や人的資本理論
【出典】〔礼記・学記〕
鬼が出るか蛇が出るか(おにがでるかじゃがでるか)
先がどうなるかわからず、不安や恐れを感じること。
【解説】不確実性の高い、金融市場や国際経済の動きについては、先の展開を読むのはなかなか難しいものです。
鬼に金棒(おににかなぼう)
もともと強いものに、さらに強さが加わること。
【解説】資本やブランドなどをすでに持つ企業が、新たな技術や制度的優遇などを得ると、競争優位がさらに強化されます。
鬼の居ぬ間に洗濯(おにのいぬまにせんたく)
権威や監督者のいない間に、自由を満喫すること。
【解説】規制や監視の手が緩んだときに、個人や企業が自由な行動を取りやすくなる状況。経済的には「モラルハザード」の関係とも読み取れます。一定の監視が市場における健全性を保つという視点も必要です。
【英語】When the cat is away, the mice will play.(ネコの留守にネズミは遊ぶ。)
溺れる者は藁をもつかむ(おぼれるものはわらをもつかむ)
切羽詰まった人は、どんなに頼りないものでも助けとして縋ろうとすること。
【解説】経済的に追い詰められた個人・組織・国家が、信頼性や合理性の低い手段に走る傾向を表しています。これを防ぐための制度設計、セーフティネット、情報提供が必要です。
【英語】A drowning man will catch at a straw.の訳語。
終わり良ければ総て良し(おわりよければすべてよし)
最終的にうまくいけば、それまでの失敗や困難は問題にならないということ。
【解説】プロジェクトや政策の評価では、途中の過程も重要ではありますが、最終成果が大きく評価を左右します。
【英語】All’s well that ends well.の訳語
恩を仇で返す(おんをあだでかえす)
助けてもらった相手に、逆に害を与えるような行為をすること。
【解説】信用や他者と良好な関係が前提の社会で、このような裏切りは大きなリスクになります。「囚人のジレンマ」や「繰り返しゲーム」で、裏切らないことの大切さを説明することができます。
←え < ![]() か→
か→
「あ・い」はこちから