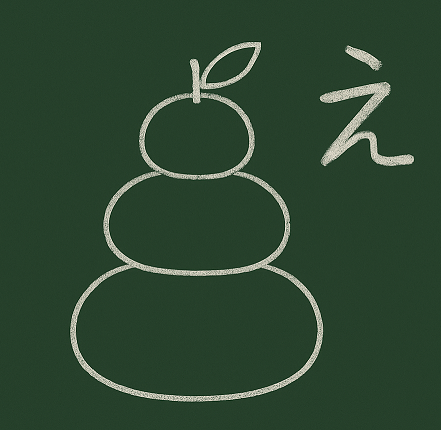
「え」ではじまるビジネス、経済学関連の格言や言い回しです。
得手に帆を揚ぐ(えてにほをあぐ)
自分の得意分野において、好機が訪れたときに勢いに乗って行動すること。
【解説】得意な分野や自分に向いた状況が整ったとき、ちょうど風を受けて帆が進むように、スムーズに物事が運ぶ状態を表しています。ビジネスでも、自分の強みが時流に合致したときに一気に伸びる好例です。いろはがるた(江戸)のひとつです。
江戸っ子は宵越しの銭は使わぬ(えどっこはよいごしのぜにはつかわぬ)
江戸の人は、その日に得たお金をその日のうちに使い、翌日に持ち越すことはしないというたとえ。
【解説】経済学的には、将来より現在の消費を優先する「時間割引率の高さ」を示す行動様式とも言えます。短期志向の消費傾向や、フロー重視の価値観にも通じます。「江戸っ子は宵越しの金は持たない」ともいいます。
絵にかいた餅(えにかいたもち)
見た目や理屈は立派でも、実際の役には立たないもの。
【解説】実現性のない計画や、空論だけのアイディアに対する批判的な言葉としてつかわれます。経済学では、予測モデルや理論が現実に適用されないケースで使われることがあります。特に政策論で、絵空事ではなく実効性を問う姿勢が重要です。「画餅」ともいいます。
蝦で鯛を釣る(えびでたいをつる)
わずかな投資で大きな利益を得ること。
【解説】少ないコストで最大のリターンを狙う行為を表すことわざです。経済学では「投資の効率」や「費用対効果(コストパフォーマンス)」と関連します。戦略的行動や情報の非対称性を利用して、利益をえることにもつながります。略して、「えびたい」ともいいます。
栄耀の餅の皮(えようのもちのかわ)
贅沢に慣れた人が、さらに不必要なまでの贅沢をすること。
〔ぜいたくに慣れると、餅の皮までもむいて、あんばかり食べるようになってしまうことからきています。〕
【解説】必要以上の消費や嗜好品への依存を風刺したことばです。贅沢に限界はあるのか、消費は飽和するのか?、過剰な生活水準の維持コストなどのテーマと関連づけられます。なお、所得が増えると同時に支出も増えてしまうことを「ライフスタイルインフレーション」といったりもします。
遠水近火を救わず(えんすいきんかをすくわず)
どれほど大きな助けでも、遠すぎると間に合わず、役に立たない。
【解説】緊急時には近くの手段が重要であるという現実的な警句です。「即応性」や「取引コスト」、あるいは「情報伝達の遅延」などの問題と結びつきます。
【出典】〔韓非子・説林上〕「火を失して水を海より取らば、海水多しと雖も、火は必ず滅えざるなり。遠水は近火を救わざるなり。」
縁の下の力持ち(えんのしたのちからもち)
人知れず、陰で努力して支えている人。
【解説】直接は目立たなくとも、重要な役割を果たしている存在への敬意を込めたことばです。企業や組織でいえば、裏方やインフラ部門のように、表には出ないが成果に欠かせない部分です。経済構造でいえば、「外部性」の提供者や「公共財」の供給の影の担い手などと解釈できます。いろはがるた(京都)のひとつです。
【注】もとは、「せっかくの力持ちも、縁の下にいたのでは認められない。他人のために陰にあって骨を折るばかりで、世の中に知られない」ことをいい、ほめことばとしてはつかわれなかったようです。
遠慮なければ近憂あり(えんりょなければきんゆうあり)
将来への配慮がなければ、目の前に困難や災難が現れるということ。
【解説】目先の利益や快楽ばかり追い求めると、やがて大きな問題を招くという教訓です。経済では、短期的には最適であっても長期的には不整合が出てくる場合があります。この長期的な視点は、「持続可能性」や時間整合性の問題などにむすびつきます。財政政策、社会保障、環境政策などでは、この考え方が重要です。
【出典】〔論語・衛霊公〕「子曰く、人、遠きを慮(おもんぱかり)無ければ、必ず近き憂いあり」
←う < ![]() お→
お→
「あ・い」はこちから