←前

突然の来客です。
続きを読む 04「いざかや」調査(特別の来客)
投稿者アーカイブ: mikumaku
お
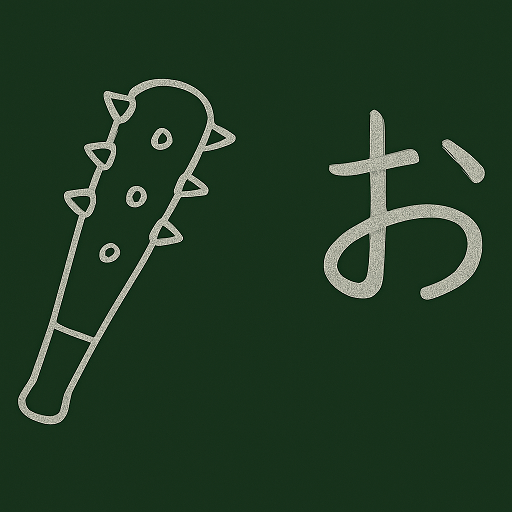
「お」ではじまるビジネス、経済学関連の格言や言い回しです。
続きを読む お
03「いざかや」調査(数日後)
←前
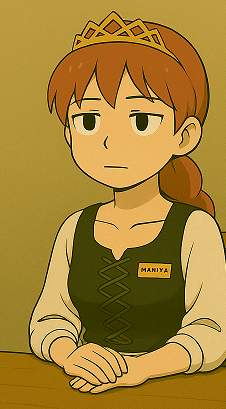
調査をはじめてしばらくたってからの様子です。
続きを読む 03「いざかや」調査(数日後)
え
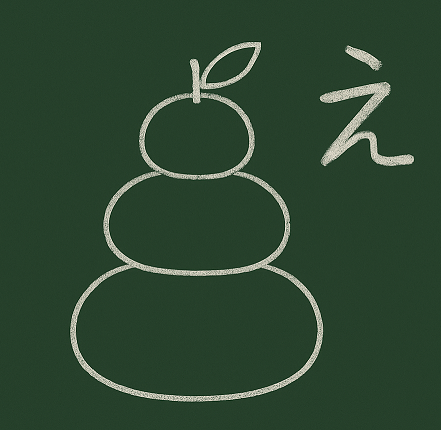
「え」ではじまるビジネス、経済学関連の格言や言い回しです。
続きを読む え
「物語」と「中学の教科書」で経済をまなぶ。
←前

突然の来客です。
続きを読む 04「いざかや」調査(特別の来客)
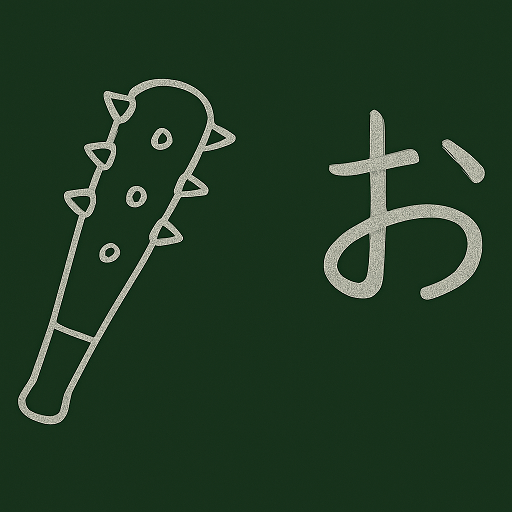
「お」ではじまるビジネス、経済学関連の格言や言い回しです。
続きを読む お
←前
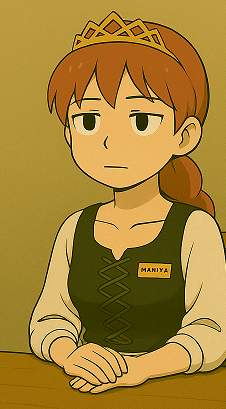
調査をはじめてしばらくたってからの様子です。
続きを読む 03「いざかや」調査(数日後)
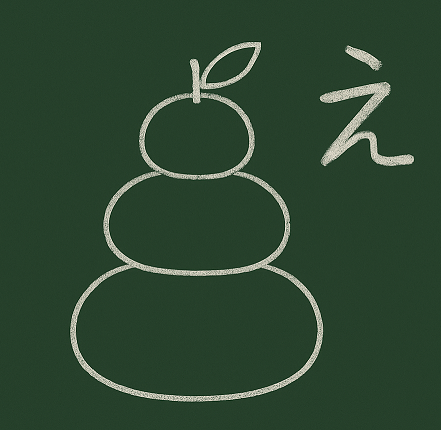
「え」ではじまるビジネス、経済学関連の格言や言い回しです。
続きを読む え